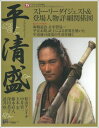平清盛 第39回「兎丸無念」
長くこのドラマの中で準主役のような待遇を受けていた兎丸も今回、ついに終了します。この人物が本当に存在していたのかどうかは引っかかる部分ではありますが、それでも清盛に誰も物言いをできなくなるほど権力が高まった状況において、対等な立場で清盛に意見をいうことができる唯一の人物であったことが、彼の存在価値のひとつだったのだと思います。
そんな兎丸は、大輪田の泊の普請作業について無茶苦茶なスケジュールをいう清盛に、マジギレしてしまいます。このような早く完成させて欲しいという要望元と、依頼先の関係というのはいつの時代も変わることのない普遍的なもの。このような状況では、限られたリソースで何を優先するのかを建設的に議論する必要があります。しかし兎丸の性格上、喧嘩別れすることになってしまい、それが永遠の別れになってしまうのです。
禿が襲う様子については、これまで細かく描写されてきませんでしたが、今回それが明らかになります。串のようなもので相手を指し示すし、それに気を取られている間に針のようなもので相手に突き刺す。非常に無残な状況です。これに対してなんの罪悪感もなく、むしろ清盛を尊敬するまなざしを向ける禿に清盛は自分がしてきたことが間違っているということを悟ったのでしょう。時忠にすぐにやめるように指示し、時忠は無念な表情で禿の装束などを始末しています。
兎丸はこれで亡くなってしまうのですが、清盛がこれまでの習慣である人柱をたてることをやめ、代わりにお経を書いた石を沈めることにしました。こういったさりげないことでも改革しようという思いが平氏の世の中につながったのではないでしょうか。
しかし、物語中でも語られていましたが清盛は残りの人生の少なさから生き急いで、自分の目指す国つくりを成し遂げようと多くの犠牲を払い始めたように思います。歴史的に見ると1代でものすごくリーダーシップを発揮する者は多く登場するのですが、その後も継続的に繁栄するのは必ずと言っていいほど、創業者が後継者の育成を怠っていないことにあります。
清盛にとって後継者は重盛ですが、ここ数回ほとんど登場しません。今回も台詞があったかどうかレベルの影の薄い存在になっています。こうなると平氏は清盛が亡くなったら本当にまずい状況になり、不平不満を抱く人々を抑えることができないでしょう。そんなことを暗に感じさせる内容が含まれていたのではないかと思います。
今回の牛若と共に次回は頼朝が息を吹き返しそうな感じであり、そういった勢力が平氏にどのように絡んでくるのか楽しみにしたいと思います。
◆清盛紀行◆
兵庫県神戸市
- 兵庫区島上町(経ヶ島)
- 勝福寺
|
|
|
|||
|
|
|


![【Aポイント+メール便送料無料】NHK大河ドラマ「平清盛」サウンドトラック[CD]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famericanpie%2fcabinet%2f411111%2f4111111103.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famericanpie%2fcabinet%2f411111%2f4111111103.jpg%3f_ex%3d80x80)