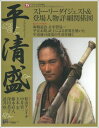平清盛 第36回「巨人の影」
物語は変わらず大きく3部構成であり、今回は王家の状況が少なく抑えられ、その分平氏に時間が割かれる状況となりました。おそらくこの構成は最後まで続いていくことになるような気がします。
まず登場したのは京の鞍馬寺にいる源義朝の子である遮那王。常盤御前との約束だからとこの場所にやって来て、そのまま僧になるつもりだったとのこと。お寺の住職は義朝のことを話したがっていたのですが、常磐御前からみると全くの迷惑で、ここに連れてきた意味を全くわかっていないとこいうことになっています。将来平氏を恨んで自分の命を失うことになってしまうということを危惧してのことだったのですが、歴史の上から見るとそのようになってしまうのでした。
話の流れ的には、このお寺の住職が遮那王に話すのではないかとみられますが、これがなかったらまた違った歴史が待っていたことになります。その時々では残酷なことであっても、時間が経過したときに時のつながりが変わってしまう不思議さが歴史の面白さではないでしょうか。この時遮那王が僧のまま終わっていたら、どうなっていたのでしょうか。
源氏の話としてはさらに頼朝の方にもスポットライトが当てられます。北条政子との出会いは果たしたのですが、まだまだお互いのことを知るのは先になりそうです。政子の父親がブロックをかけていましたが、それも時間の問題でしょう。その出会いを果たしたとき、頼朝はどのように復帰することになるのか見物です。
平氏に関しては、題名にもありますが完全に清盛の存在が大きすぎて重盛もどうしていいのか分からない状況にあります。清盛だって忠盛の影響力に負けそうになりながらも、武門を率いて一人前になって行ったのですが、重盛はその壁が大きすぎたのでしょうか。
周囲に信頼されるようになるのは時間がかかります。その時間がものすごく早く過ぎていて、清盛のときのようにもう少しだけゆっくり見守ってあげようと思ってしまうのですが、作者は重盛の求心力のなさを強調したいのかもしれません。それを示す出来事を今回だけでも複数回用意しています。
清盛も重盛に家督を譲るのであれば、もう少し思っていることや方向性を示し、アドバイスをしてあげればいいのに、多くを語ろうとしないように見えます。重盛もものすごくツライ立場にあったことでしょう。比叡山、後白河法皇、藤原摂関家など数多くの難敵に自分なりの方向性をどのように指し示していくか、その独自性に注目したいと思います。
◆清盛紀行◆
広島県廿日市市
- 厳島神社
- 清盛神社
|
|
|
|||
|
|
|


![【Aポイント+メール便送料無料】NHK大河ドラマ「平清盛」サウンドトラック[CD]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famericanpie%2fcabinet%2f411111%2f4111111103.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famericanpie%2fcabinet%2f411111%2f4111111103.jpg%3f_ex%3d80x80)