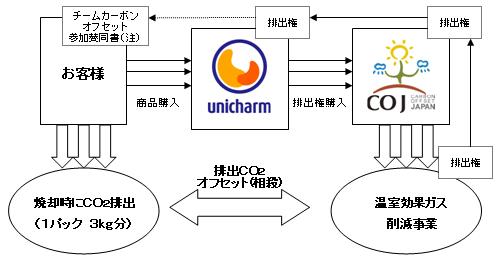出現!ハイブリッド猫の秘密

今や私たちの暮らしとは、切っても切り離せない存在となったペットたち。最近は小型犬の人気が高まっていて、中でも人気の犬同士を掛け合わせた”ミックス犬”と呼ばれる犬がよく売れているそうです。
その背景には、飼い主の「誰も飼っていないようなペットが欲しい!」という要望が、世界的にこのような掛け合わせたペットの増加を生んでいます。
アメリカでは、野生動物と家ネコを交配させた「ハイブリッド・キャット」が人気で、その象徴ともいえるのが、ヒョウのような猫“アシェラ”(ASHERA)という品種。野生のアジアンレオパードという山猫に家ネコ、さらに野生のアフリカンサーバルを掛け合わせ誕生した、究極のハイブリッド・キャットです。
サーバルは一時自宅でペットとして飼う人が多くあり、ボブサップさんも家で飼っているのですが、世話がものすごく大変ということで、改良が必要となりました。
日本でもアシェラを販売する話も出ていて、その時の予想価格はなんと、300万円以上!!ここまで行くとすでにブランドものとなっていて、ステータスシンボルとして、誰かに自慢したくなる気持ちはよく分かります。
一方、ペット人気の陰には、ペットが人を襲う事故や、無理な交配により障害を持つペットが増えるなどといった問題も起きています。
ウルフドックと呼ばれるオオカミと犬を交配させた犬による人への被害が、アメリカでは後を絶たなくなり、年々増加傾向にあります。この事故を受け、ハイブリッドキャットの飼育を禁止するという法律ができる州も登場する程になってしまいました。
一度コントロールが効かなくなると、飼い主でさえ威嚇の対象にします。もはやここまでくると野生動物を飼っているようなものです・ペットと私たち人間の良い関係とは何か、を改めて考える必要があります。
日本でも、人気のゴールデンレトリバーの関節がはずれやすくなったり、股関節の異常が発生したりしています。急に人気が出たため需要が追いつかず近親繁殖を繰り返すことによってこのような異常種が増えてしまっているのです。
新たな取り組みとして、血統種に交配させ異常種の繁殖を食い止めようとする動きも始まっているのですが、全体の数があまりに多いため、これからという印象です。
動物はブランドもののバッグでも、靴でもありません。人に自慢したり優越感を味わうのも構わないと思いますが、それ故本来の自然であり得ないような品種を多く生み出すことによって、最後は自分たちにしっぺ返しが来るのではないでしょうか。
飼い主側の意識が改めて問われているのだと思います。
| ネコ好きが気になる50の疑問 飼い主をどう考えているのか? 室内飼いで幸せなのか? (サイエンス・アイ新書 25) (サイエンス・アイ新書 25) (2007/06/16) 加藤 由子 |