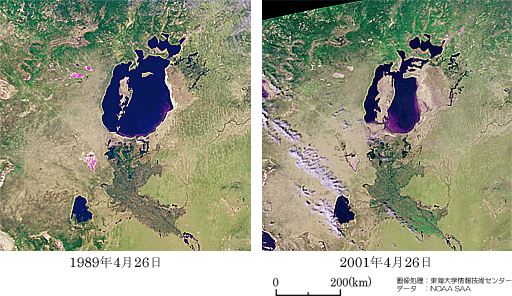素敵な宇宙船地球号 ?白神山地 ミクロパワーの奇跡?
最近、アメリカで騒然となったことがある。その原因は、「トランス脂肪酸」
これは、マーガリンなどに含まれる植物油に人工的に水素を加え、固形化したものに含まれる物質で、健康を害するとしてニューヨークで使用制限、または使用禁止になった物質だ。
この物質をとりすぎると、明確に出るのが腎障害だ。その他アトピーやアレルギーなど多くの疾患の原因となることが分かってきた。
このように、近年人工の物質が多く我々の食べるものに含まれていて、食の安全が危ぶまれている。
そこで注目されているのが白神山地だ。日本初の世界遺産で8000年前から手つかずのブナの原生林が広がっている。ここに食の危機を救う物質が必ずあるはずとして、秋田県食品総合研究所の高橋慶太郎さんを中心とした研究チームが研究をしている。
1999年、高橋さんは腐葉土からスーパー酵母菌を発見した。それが白神こだま酵母だ。
この酵母を使った白神酵母パンは、牛乳やたまごを使わないのでアトピーやアレルギーに影響を与えないということで密かに人気を広げていった。さらに白神こだま酵母に曲を聴かせるとより活性化するという。番組内では津軽海峡冬景色を聞かせていた。おいしいパンになったらしい(笑)。やはり日本の酵母だから、という理由に思わず笑ってしまう。
白神山地の腐葉土は100年で1cmという途方もない時間をかけて堆積する。高橋さんの研究チームは10年間で4500カ所の腐葉土を採取し微生物の秘密を調査してきた。
この白神山地の微生物の特徴は低温に強く、たくましい生存力があることなんだが、なぜ強いのか?
それは、?80度でも細胞の凍結を防ぐトレハロースという糖質の存在があった。白神山地の微生物に共通するのは普通の酵母の5倍を持つということ。このトレハロースを使って、和菓子、保湿力、移植手術なら臓器機能の低下、細胞の酸化や劣化、加齢臭等を防ぐ力があるというのだから驚きの物質だ。
白神山地にはまだそんな微生物がたくさん眠っているはずということで研究を続け、2003年6月、またもや朽ちたブナの木からスーパー乳酸菌を採取した。それが作々楽(ささら)
この微生物は、抗菌作用があり、悪玉菌を撃退する採用があり、秋田県の伝統的な漬け物であるなた漬けが、3日持たなかったのに、この作々楽を使用すると1ヶ月持つようになったという結果も得ている。
さらに、2006年、乳酸菌Xという物質を発見した。これは4度で3日ほどで大量に増殖する能力を持つ。他の雑菌が増殖できないので、すごく抗菌性のある食品を作れるようになるといった利点がある。
このようにまだまだ白神山地には我々が知らないようなたくさんの微生物が眠っていて、今は治すことができないような病気も治すことができるようになるかもしれない。
ただし、酸性雨や温暖化でブナ林がいつまで持つのかが不安と高橋さんは話す。8000年という、悠久の時をかけ育んできた大切な原生林を、我々が壊すようなことをしては決してならない。後世に生きる子供たちに健康なままに白神山地のブナ原生林を受け継いでいくことで、はじめて自然から恩恵をうけることができるのだと思う。