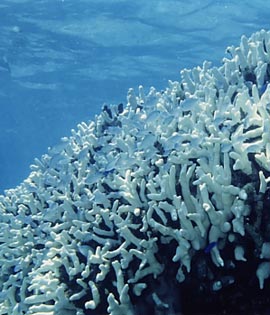居酒屋で人気のメニューとして、
・梅干し入り芋焼酎
・ホタテのバター焼
があります。この季節、これで一杯やるのは本当に至福の時です。
でもこれらの元となる、焼酎、梅干し、ホタテが、今ある問題がわき上がっています。それは、作る途中で出た様々な廃棄物の処理についてです。これからこれら3つの廃棄物の問題について見ていくことにしましょう。
■焼酎かす
日本では、鹿児島を中心に焼酎を多く生産しています。ここ最近の焼酎ブームにも乗っかってその生産量も飛躍的に延びています。
ところが、焼酎の生産中に焼酎かすとよばれる廃棄物が出てしまいます。1リットルの焼酎を作るのに2リットルの焼酎かすが出てしまいます。1年で換算すると50万トンもの焼酎かすが生成されてしまうのです。
これまでは、家畜のえさとして地元で上手に消費していたのですが、だんだん消費しきれなくなって海に捨てるようになってしまいました。これまではそれでよかったのですが、1996年のロンドン条約議定書採択によって、原則としてすべての海洋投棄を禁止することとなってしまいました。
芋焼酎メーカーはこれにあわてました。魚のえさになると思って罪悪感を感じることなくやっていたことが問題であるとして、もうできなくなってしまったのです。
焼酎かすの再利用の方法を研究sている鹿児島大学の林教授によると、焼酎かすからできるブトキシブチルアルコールを有効活用することができるとのこと。これを使って焼酎かすに乳酸菌を混ぜて飼料としてリサイクルすることで解決したかに見えました。
ところが、さらなる焼酎ブームに乗って、飼料プラントの加工能力を超えてしまったのです。
鹿児島大学の江幡さんを中心とする研究チームは、産卵用タコつぼとして焼酎かすをリサイクルすることに成功しました。焼酎かすではなく、焼酎副産物として再利用することができれば、地場産業の活性化にも役立つと江幡さんはいいます。
■梅干しの調味液
塩で漬けただけのしょっぱい梅干しが主流でしたが、今では一度漬けた梅干しから塩分を取り除く処理が追加になりました。その調味を行う調味液が廃液として出てくるのですが、これを海に捨てていました。その量は年間5万トンもの量になります。
和歌山県みなべ町の東農園では、陸上でこの調味液を処理する施設を総工費1億円で作り、さらに梅生産に関わるものをリサイクルしようとして梅科学研究所を設立しました。
調味液をリサイクルして、できたものを北海道網走郡へ持って行く東社長。
行き先は牛舎です。
牛は鉄分やミネラルを取らないといけないので、これまでは塩を輸入していたのですが、この調味液のリサイクル塩で代用することができそうな感触を持ちました。
■ホタテ貝の貝殻
ホタテの貝がらの量は年間4?5万トンにもなります。
使い道を模索していたところへ、青森エコサイクル協同組合はホタテ貝の貝殻から酢酸カルシウムを作りリサイクルすることに成功します。
この使い道は、凍結防止剤。
冬の雪道に撒くことで、凍結を防止することができます。今までは塩素系の薬品を使っていましたが、塩害の被害を伴ってしまうため、このホタテの貝殻の凍結防止剤は最適といえるものでした。
課題は、この生産プラントの生産能力が年間6000トンであること。年間に廃棄される貝殻の20%弱であることから増産が求められるでしょう。
2007年4月。
改正海洋汚染防止法が施工され、今まで不用意に海洋投棄していた様々なものはすべて禁止されました。「不法投棄を許すな」として、海上保安庁も定期的に監視しています。
ここに挙げた3つは、まだまだ氷山の一角です。このほかにも海洋に投棄されている物、陸上で投棄されているものは数多くあるでしょう。
でも、それは必ずリサイクルする道が残されているのです。廃棄物は何らかの手を加えることによってまた命を取り戻すのです。まだ、生き返らせるのにコストがかかってしまうので、それを実施することに二の足を踏んでしまうかもしれませんが、逆にリサイクルしていることを社会にうまく伝えることができれば、企業のイメージが向上し、違った形で利益をもたらすことになるんだと思います。
自分たちも、このようにリサイクルをして懸命に地球環境を守ろうとしている企業、製品を応援していくことによって、環境問題の個人レベルの取り組みの一つになるのではないでしょうか。
※いつも見ている素敵な宇宙船地球号のDVDボックスが発売されました。
この10年で地球環境は劇的に変わりました。この10年間、世界各地の環境問題や自然保護に取り組む人々を取材してきた「素敵な宇宙船地球号」。
番組が始まった頃は、耳慣れなかった“地球温暖化”という言葉も、いまや日常会話に登場するようになりました。
番組がスタートしてから10年・・・
各テーマで取り上げた今と昔を降り返り、未来に向けて何をするべきか改めて考えていく10周年スペシャルシリーズをDVD化。
さらに、番組を象徴する企画で現在も継続中の旧芝川再生プロジェクト「大都会ドブ川の奇跡」も収録。