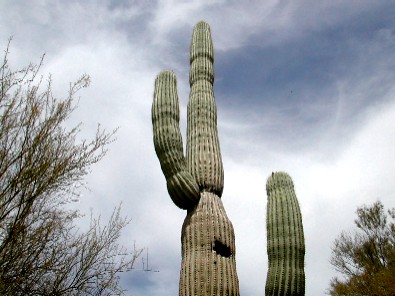空から地球を記録する男
ヤン・アルテュベルトラン。
62歳になる彼は、世界でも有名な環境航空写真家です。「人類と自然の共存」をテーマに世界の隅々を記録した作品は10万点を超えます。
ヤンさんの作品が来年「HOME」という映画として公開されます。ヤンさんの写真は、そのどれもがメッセージを持っており、世界中の人々がそのメッセージに心を揺さぶらされ、そして地球環境の危機感を改めて感じるのです。現在、ヤンさんの作品は34カ国で特別番組として放送されています。
熱気球から見た壮大なサバンナに心を突き動かされたのがきっかけで、それ以来世界中の空から撮ってきた写真は既に100万点を超えています。
アフリカでは、人間と動物の共存を実現する上での大きなほころびを映し出してきました。
ヨルダンの首都アンマンでは、現在民族紛争以外にかかえている大きな問題、水不足を映し出してきました。アンマンでは給水車から購入し、水が必要な洗濯や掃除は週1回という状況に陥っています。同じ砂漠地帯であるはずのラスベガスではエンターテイメントとして大量の水を浪費しているのです。
フランスの海では、サークル状の養殖場で発生している食料危機の問題を表現しています。1?の魚を養殖するのに天然の魚を4?えさにするという大きな矛盾にメスを入れたのです。
世界最大の銅鉱山では、1トンを掘り起こして出てくる銅はたったの6kgをいう現実を突きつけます。自分たちの生活を守るために、地球に大きな爪痕を残しているのです・
地球の今と昔が全く違うことを伝えること、それが仕事だとヤンさんは語ります。
そんなヤンさんの映画のシーンとして東京も入れたいとして、先日来日しました。高層ビルが立ち並ぶ大都市の人々が暮らすその姿を象徴的に取りたいということで、早速ヘリコプターをチャーターし、東京、横浜の上空を映し出し始めます。
ヤンさんの写真の哲学、それは「ディテールに神様はいる」
その言葉が示す様に映像の細部にまでこだわります。パイロットと、撮影者の気持ちがシンクロして初めていい写真を撮ることができるというのです。
まず、ヤンさんが気に入った場所は横浜の大黒ふ頭です。世界一美しいインターチェンジと評し、輸出用の車が整然と並んでいる港もいっしょに写します。
次に訪れたのは、東京・築地市場。ヤンさんはマグロのセリ場が気になるそうです。マグロが世界中の海で乱獲されている事実に心を痛めていて、ここはまるでマグロの死体置き場だと嘆きます。このままとり続ければ、いずれ世界の海からマグロがなくなってしまうと不安視しているのです。
現場の人たちに話を伺うと、彼らは、獲りすぎはアメリカなどで行われている巻き網漁のほうが影響が大きいと言います。アメリカなどでは食用というよりもキャットフードなどで使われているそうです。日本ではマグロは生活に深く根付いている文化なので、難しい問題ではあります。
そして最後にヤンさんが訪れたのは、日没寸前の渋谷のスクランブル交差点上空です。信号が変わる度にこれほどの人がわたる交差点は、世界中にここしかいないとヤンさんは言います。
ここは自分が望む世界とは正反対で、消費国家日本の象徴だということでこの街を選んだそうです。20年後、この街の姿は確実に変わっているでしょうとヤンさんは警告します。
本当にそうなっているのかどうかが分りませんが、世界中で起こっている状況を客観的に見つめることができるヤンさんの警告から、自分たちが何をすることができるのかを改めて考え、そして行動しているんだということを世界中の人たちに訴えていき、さらにその動きを世界レベルまで広げていくことが大切だと思います。
来年公開の映画「HOME」に注目しましょう。
【参考】素敵な宇宙船地球号 9月15日
 |
空から見た地球―21世紀への遺産 (2000/02) ヤン アルテュベルトラン |