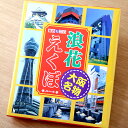「甘い香りの感じ方」の境界線
槇原敬之さんの「No.1」という曲の中に次のような歌詞が登場します。
夕暮れ僕の街には チョコレイト工場の匂いがする
いつかおいで あの河原に自転車でつれて行くよ
すごく情景が目に浮かぶ素敵な歌詞で、この曲が文字通り一番好きだというファンも多いことと思います。夕暮れ時という何となく寂しくもノスタルジックなひとときに、甘い匂いがふわっと漂ってくる街は、すごく魅力的であり主人公はそんな街に自分の恋人をよんで知って欲しいと願っているのでしょう。
そんな街に流れる甘い香りも、捕らえようによっては非常に迷惑だと考えられます。京都市の製菓会社工場の周辺に住む住民が、工場から漂う焼き菓子の甘い香りなどで苦痛を受けたとして、製菓会社と京都市に慰謝料など計約2,100万円の損害賠償を求めて訴訟を起こし、その判決は製菓会社側に支払いを命じるものとなりました。
周辺の住民の話によると、工場から出るベビーカステラやあんこ、焦げたバターの甘い臭いで窓も開けられず、干している洗濯物に臭いがつくし、機械の運転する音「ガツシャーン、ガツシャーン」という音がいたるところから聞こえてくるのが苦痛だったといいます。また、この製菓会社のあった場所は、本来であれば建築基準法で大きな工場を建てることができない場所だったそうです。
このように、同じ「甘い香り」でもそれが人々に与える感情はいいものばかりではなく、不快を与えるものもあるのが現実なのです。日本全国には工場から出るにおいが街全体を包み込んでいる場所が数多くあります。それを住民が不快に感じるか、懐かしく好意的にとらえてくれるか、その境界線は「工場が街になじんでいるか」だと思います。
地域の特産であることや、工場自体が街のシンボルであること、街全体が向上と共に歩んでいることが条件となり、そういった街とそこに暮らす方の間に信頼関係と相互依存関係が成り立っている場合に、街の顔となり受け入れられることができるのだと思います。
そうなるために、工場は地域に対して貢献をする必要があると共に住民の方の暮らしを最大限に配慮した取り組みが求められるのです。それがうまく回ることによって槇原敬之さんの歌詞に出てくるシーンは、みんなに愛される情景となって浸透していくのではないでしょうか。
【参考】京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100915000062
 |
SELF PORTRAIT (1998/11/26) 槇原敬之 |