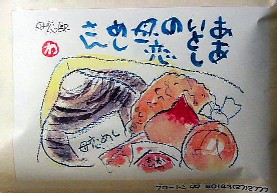バードストライクを阻止せよ!
2009年1月にアメリカ・ラガーディア空港で発生したUSエアウェイズ機によるハドソン川不時着は記憶に新しいところです。このハドソン川への緊急着陸は「ハドソン川の奇跡」として、その後サレンバーガー機長は英雄として扱われました。この事故の原因はバードストライクだとされています。
バードストライクとは、鳥が構造物に衝突する事故のこといい、主に航空機と鳥が衝突する事例を指します。飛行機でいうと離着陸の時が発生確率が最も高くなります。それは離着陸という最も不安定な工程であることと、鳥の飛行高度である100メートル以下というふたつの要素が重なることによります。
USエアウェイズ機による事故も、離陸時にガンの大群が突如現われ、左右ふたつのエンジンに巻き込まれてしまいエンジン停止状態になってしまったのが原因ということで、まさに2つのエンジンが同時という100万分の1の確率が起こってしまったのです。巻き込まれた鳥はカナダガンという鳥で、1960年代に絶滅の危機にあったこの鳥は、今や100万羽以上にまで復活しています。
バードストライクの歴史はかなり古く、ライト兄弟がすでに鳥との衝突にあっているということから、人間が人工の翼を手に入れ、鳥の領域に足を踏み入れたときからの宿命なのです。このバードストライクに対して、日本ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。3つの空港についてその取り組みを紹介します。
◆有明佐賀空港
この空港は国内でバードストライク発生確率が最も大きいとされています。その原因は有明海にあります。有明海に広がる干潟は野鳥にとって格好のエサ場となり、ハマシギ、ダイシャクシギなどの野鳥が住み着いています。
バードストライクを発生させないための国際的に共通的な取り組みは、空港内に鳥を寄せ付けないようにすることだそうです。それに習って有明さが空港では電子爆音機やガス爆音機を使うと共に、1日12回程度空港付近で車のクラクションを鳴らしています。この地道な方法によって今まで事故は起こっていうのですから、利用者としても感謝すべき努力といえると思います。
◆中部国際空港
この空港には、2007年に1万羽以上ものウミネコが住み着いてしまい、空港を占拠してしまいました。原因は空港の環境対策として取り入れた空港付近の海の底に植えられた海藻によって多くの魚が集まり、その結果として鳥も増えたことにあったのです。
鳥は滑走路にもくるようになり、そのために一時飛行機の運行がマヒする事態にまで発展してしまいます。空港関係者は酢酸をまいたりして様々な対策を打ちますが効果は数日だけ。そこで環境コンサルタントの橘敏雄さんにアドバイスを求めます。橘さんは30年以上バードストライク対策を行ってきたエキスパートなんですが、彼によると中部国際空港のウミネコは完全に安心しきっているとのこと。
これを撃退するために利用したのが、デストレスコール(ウミネコの悲鳴音)が入ったカセットテープです。ウミネコの、仲間の悲鳴が聞こえると集まってくる習性を利用し、集まったところで空砲を撃ち込みここが危険であることをウミネコに知らせるのです。この結果、突然ウミネコは出現しなくなりました。素晴らしい効果です。橘さんによると、鳥との真剣勝負が大切だといい、その勝負は今も続いています。
◆羽田空港
2010年10月に開港予定で現在建設中のD滑走路対策が進められています。橘さんによると、多摩川河口干潟にはスズガモやヒドリガモといった野鳥が生息しており、、夜間活動する鳥が多く衝突する危険性が高まるといいます。この危険に対処するために、JALフライトシミュレータでもバードストライクを想定した訓練が年間3回行われています。
鳥たちに罪はありません。大切なことは命を落としてしまった鳥から、人間が何かを学び少しでも犠牲になる鳥を減らすことにあります。バードストライクは、飛行機相手だけでなく、ビルの窓ガラスに激突する鳥や風力発電のプロペラにかかる鳥もいます。これらに対して、ガラスの角度を30度傾けたり、特殊に加工したプロペラを採用したりしながら試行錯誤が必死に行われています。
空は誰のために?
そんな命題を背負いながら、人間と鳥が共に生きる道を模索する試みはまだまだこれからも続きます。
【参考】素敵な宇宙船地球号 2009年5月3日
 |
生まれ変わる首都圏の空港 (2009/03) 杉浦 一機 |