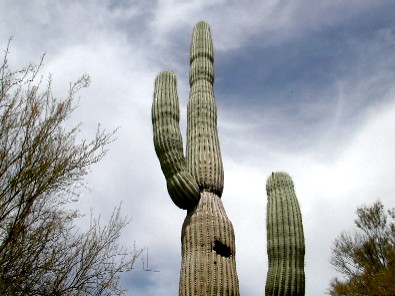大都会の侵入者を捕獲せよ!!
アメリカの大都会、夜遅くに街の中に姿を見せるのはアライグマ。彼らはセントラルパークの一角に暮らしていて、雑食のためこの大都会でもたくましく生きています。
しかし、ニューヨークでは今このアライグマを巡って大問題となっています。アライグマに接触すると、様々な病気に感染する危険性をもっているというのです。例えば、狂犬病、アライグマ回虫などの感染症が挙げられ、亡くなった人も存在します。
街中には、アライグマへの注意を呼びかける張り紙がたくさんあります。アメリカではアライグマは、ネズミやゴキブリと同様に感染症を持つ生物として同じ扱いを受けているのです。
このことは日本人にとってすごく意外に感じるかもしれません。アライグマはアニメでも登場するほどかわいらしい存在として、日本では扱われてきました。
しかし、アライグマは牙がすごく、凶暴であることを知っている人はあまり多くないと思います。なかには手を何針も縫ってしまうケガをしてしまった人もいるくらいで、そのあまりの凶暴さに、手ばしてしまう人も多く存在します。
そうやって野に放たれたアライグマは、野生動物に多くの被害を与えることになります。千葉県では在来種の亀100匹がかみ殺される事件もアライグマを起因として発生しました。繁殖したアライグマの猛威は都市部にも広がっています。
アライグマは危険な動物であり、感染病をもっている危険性もあるので、気軽に触ったりしてはいけないのです。改めて再認識しておく必要があります。
外来種は、東京と神奈川の間を流れる多摩川でも多く発見することができます。川崎漁協によると、多摩川だけで100種類以上の外来種がいるそうです。
<多摩川にいる外来種>
・グッピー
・エンゼルフィッシュ
・タイガーオスカー
・レッドテールキャットフィッシュ
いずれも南米など外来種であり、日本にいるはずのないものばかりです。多摩川にいる原因は大きく2つ。一つ目が、観賞用に買った人が多摩川に捨てていること、そして2つめは、多摩川の水温が高いのでそういった魚が生き続けられる環境であることがあります。
水温が高いのは、温暖化も影響しているのですがその多くは工場排水や下水排水によって水は綺麗になっても水温が高いまま多摩川に放流されることが挙げられます。
大田区の呑川でも、肉食魚アリゲーターガーが悠々と泳いでいます。捕獲したアリゲーターガーの体長はなんと114cm。大きくなると3mにもなるそうです。
このように外来種による被害は大きくなるばかりです。しかし、一番かわいそうなのは動物や魚たちなのです。彼らに罪はありません。欲しくなったら飼い、いらなくなったら捨ててしまうその人間の身勝手な行動が、自然のサイクルを壊しているのです。
自分が珍しいものを飼うんだと決めたとき、最後まで責任をもって飼うという当たり前のことを、忘れてはいけないのです。
 |
ぜったいに飼ってはいけないアライグマ (1999/10) さとう まきこ杉田 比呂美 |