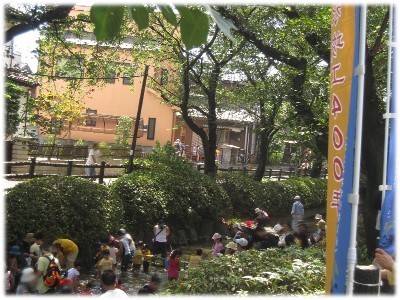理想のイクメン像と求められる姿
最近、にわかに積極的に子育てに参加するイケメンパパのことをさす「イクメン」という言葉が世間を賑わせ始めています。雑誌やテレビなどでファザーリングジャパンの安藤哲也さんが登場し、パパが積極的に子育てに参画しようとする動きが活発化しているといいます。2010年6月からは厚生労働省によって男性の子育て参加や育児休暇の取得促進を目的とした「イクメンプロジェクト」も発足していることからも分かるように、国レベルでイクメンに対する活動が広がっているのです。
そんな中、オリコンが「イクメンだと思う男性タレントは?」というアンケート結果を公表しました。そのランキングから、世間が認めるイクメンに必要な要素とママから求められる理想のパパ像について、改めて把握し今後の子育ての参考にしたいと思います。
◆◆イクメンだと思う男性有名人TOP5◆◆
1位: つるの剛士
2位: 照英
3位: 杉浦太陽
4位: 土田晃之
5位: 薬丸裕英
このランキングから分かることは、子供が多くいてテレビなどで子供と一緒に色々遊んでいる様子を楽しそうに話す人や本や雑誌、テレビ、Webなどで子育てに必要な情報を提供している人が多くランキングしているような気がします。
例えば、1位のつるの剛士さんは「つるの剛士の読み聞かせ絵本 ぴっぴっぴー!」など育児書を執筆し、子供のために育児休暇を取得していることが話題になりました。世間からも、子ども同伴の結婚式が素敵だったことや、育児休暇に対してイクメンとして最もふさわしいという意見が多く寄せられたようです。
また2位の照英さんは、NHKの「すくすく子育て」で楽しそうに育児状況を話しその体型からは似つかわしくないほど、子供に対してメロメロになった姿を見せてくれるところが好感度大なのでしょう。親として自分の子供を見るときの目というのはプライベートでは少なからずこうなるのですが、それをテレビという場でも隠さずに出すということに、イクメンとしての素質を感じます。
ランキングからわかるイクメンとして大切なことは、やはりママのサポートをしてあげることができる最低条件をクリアした上で、自分の子供がかわいいという自分をさらけ出し、その上で一緒に遊ぶことに楽しさを感じることなのだと思います。子供を見ているだけで嬉しくなるし、一生懸命話をしている姿もかわいいですし、そんな子供と一緒にいたいという気持ち。いつまでも感じていたいものです。
◆◆妻が 「イクメン」に求めることTOP3◆◆
1位: 子どもの相手をしてくれる (90.8%)
2位: ぐずっている子どもをあやしてくれる (84.8%)
3位: お風呂に入れてくれる (80.0%)
また、奥さんが夫に求め子どもとの関わり方ランキングでは、家事を手伝うことは意外にもランキングにはなく、子供と積極的に関わって欲しいという願いが強く出ています。仕事でどうしても帰りが遅くなってしまうこともあり、日頃は奥さんがやってくれていることが多いのですが、それでもずっと一緒にいると気分転換も必要です。そんなときに可能な限り子供の相手をすることによって、少しでもストレスの緩和につながれば、結果的に家族が楽しく過ごせることにもつながるのだと思います。
大切なことは相手をするという何となく上から目線での考え方ではなく、「一緒に楽しむ」という風に考えること。自分が一緒にいてつまらなければ子供にもそれは必ず伝わってしまうものですし、自分も長続きしないでしょう。いつもできることではありませんが、少なくともそういう風に考えるように意識したいものです。
また、ぐずっている時は必ずたくさんあり、多くの場合ママの方に子供は向かいます。父親の力のなさを痛感する一場面なのですが、それもいつもいつもでは奥さんとしては精神的に参ってしまうでしょう。そんなとき、自分も違った形でぐずる子供の気分転換をかってするのがいいと思います。機嫌を直してくれるかどうか分かりませんが、奥さんとしてはぐずられる矛先が自分から離れるので、精神的にずっと楽になるはずです。
このように、子育ては夫婦の間でうまく役割を分担しつつも、時に奥さんの負担を少しでも軽減してあげ子供と一緒になって遊ぶのは理想のイクメン像の1つの形なのではないかと感じます。何事も楽しくすることができれば、いい思い出もそこからたくさん生まれるし、自分たちも人間的にも成長できるのではないでしょうか。
【参考】oricon life http://life-cdn.oricon.co.jp/news/80021.html
 |
つるの剛士の読み聞かせ絵本 ぴっぴっぴー! (2008/11/14) つるの 剛士 |