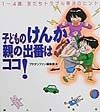ケンカの上手な仕方
夫婦やカップル、友人など関係が深まれば必ず、ケンカが起こります。自分が考えていることと相手が考えていることが食い違っていたり、自分が絶対にやって欲しくないということを相手にされたりすると、どうしても口調は強くなりがち。その強い口調によって些細なボヤで済んでいたものが大火事になってしまいます。
でもこのケンカ自体は決して悪いものではないのです。自分が伝えたいことがきちんと相手に伝わってお互いに理解することができれば、ひとつ成長した関係を築くことができると思います。大切なのはケンカの後処理を誤らないこと。
そのための上手なケンカの仕方について紹介します。ケンカをするときのポイントは3つのSに集約することができます。以下その3つについて示します。
<ケンカをするときの3つのS>
◆その1: ショート (短く)
クドクド、ぐちぐち、何度も同じことを言われると段々イライラ度が増してきてしまい関係修復が簡単ではなくなっていきます。怒るときは短く、が基本です。
◆その2: シャープ (鋭く)
怒りの論点が鋭く核心を突いていること、ポイントをしぼっていることが重要です。。怒りたいことがたまっていた場合、派生していろんなことを言ってしまいがちですが、怒るときは鋭くビシッと言うようにします。
◆その3: スマイル (笑顔)
怒っている時に笑顔を作るのは難しいですし、感情的になっている時は笑顔なんてとても無理と思うでしょう。そんな時、少し考えてみます。
・あなたの怒りはそんなにむきになって怒らなくてはいけないことですか?
・少し冷静になればもう少し違う言い方ができると思いませんか?
ヒステリックになり、言葉で相手を捲くし立てるより、笑顔で優しい言葉づかいの方が、相手だって素直に聞くことができます。
あわせてケンカの時に絶対に言ってはならない、火に油を注ぐような言葉というものも存在します。それをケンカ時の3つのタブーとしてまとめると、以下のようになります。
<ケンカ時の3つのタブー>
1. 相手の人柄を否定する発言
2. 相手の大事な友人や趣味にケチをつける
3. 別件を持ち出して怒る
誰でもプライドを持っていて自分の友人に対しても誇りがあります。それを傷つけられてしまうことによってまるで自分が責められているかのような感覚を覚えてしまいます。些細なことがきっかけでも大きなケンカになってしまう最大の要因はここにあるのです。
始めにも言ったようにケンカは関係を強くするためにどうしても必要なのです。それをいいケンカと悪いケンカに分けるとすれば、当然前者の方がいいに決まっています。それは自分の一番にいたいことにしぼってそれ以外を持ち出さずに、さくっと切り上げること。そして自分が悪いと思ったらすぐに謝り跡に引きずったりしないこと。
簡単なようでいてなかなか難しい行動ではありますが、何も言えずに恐れるばかりいるのではなく、勇気を持って柔軟に対応できる人間になりたいものですね。
【参考】nanapi http://r.nanapi.jp/5002/

【長さは2パターン・ペアでも少しゆるめが好きな方にも】《友達と仲直りしたいあなたに》“レッ… 価格:3,800円(税込、送料別) |

二人の気持ちをもと通りに戻したい【天然石屋さんストラップ】恋愛運恋人と仲直りできるS-SAP-0109 価格:580円(税込、送料別) |
![※お届けまで約1ヶ月程度いただきます【送料無料】[SNOOPY BOUTIQUE] スヌーピーブティック・ハ...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjewelplus%2fcabinet%2fsnoopy%2fpf080.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjewelplus%2fcabinet%2fsnoopy%2fpf080.jpg%3f_ex%3d80x80)
※お届けまで約1ヶ月程度いただきます【送料無料】[SNOOPY BOUTIQUE] スヌーピーブティック・ハ… 価格:220,000円(税込、送料込) |